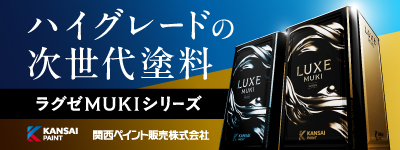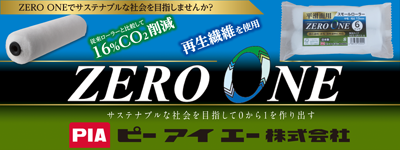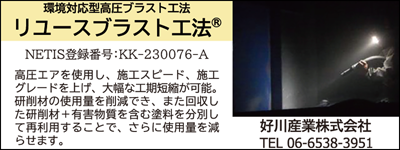▼第三次担い手3法は昨年12月から一部が施行された。受注後に資材が高騰する「おそれ」が出てきた時に、受注者は注文者に代金変更の協議を申し出ることができる。契約書では価格が変動した場合、請負代金や工事内容を変更できる旨を明記することが義務づけられた。資材の入手が困難になるなどの「おそれ情報」は、受注者が注文者に通知する義務があり、受注者は請負代金や工期の変更を協議できる。現場技術者の専任義務も合理化された。4千万円以上1億円未満(建築一式は2億円)の工事は、遠隔施工管理などのICTを活用すれば兼任ができる。
▼今年12月から施行されるのは「著しく低い労務単価等の禁止」「受注者による原価割れ契約の禁止」「工期ダンピング対策の強化」だ。まず中央建設業審議会(中建審)のワーキンググループが「労務費の基準」を作成する。WGは学識者、受注者、発注者で構成するが、基準案の作成にあたっては個別の専門工事業団体もオブザーバーとして参加することになっている。その後、今年11月頃までに中建審で基準の勧告を行う。この基準に比べて「著しく低い労務費」による見積りや見積り依頼が禁止される。違反発注者は国交相が勧告・公表する。現行では指導・監督にとどまるが、より厳しい措置が取られることになる。
▼一方で、受注者側も原価割れ契約が禁止される。従来、受注者側には規制がなかったが、ダンピングは受注者にも大いに責任がある。今回の法改正ではこの「受注者責任」を明確にした。工期のダンピングについても、従来は注文者だけが規制されていたが、新たに受注者の責任も問われる。中建審が「工期の基準」を作成・勧告し、通常必要な工期よりも「著しく短い工期」による契約は、発注者・受注者の双方の責任が問われ、違反した業者は指導・監督を受ける。
▼改正法の実効性を確保するため、建設Gメンによる監視体制が強化される。本年度から倍増された建設Gメンは取引実態を実地で調査し、改善指導を行う。毎年実施している「下請取引等実態調査」は本年度から調査対象を3万業者に大幅拡大し、違反情報を把握する。また、各地方整備局に設置された通報窓口「駆け込みホットライン」も通じて建設業法違反の通報を受け入れる。
▼今回の法改正で、将来の担い手確保に向け、技能者の処遇改善への大きなステップになることが期待される。効果は官公庁の工事から民間工事へ、大きな現場から小さな町場の工事へ波及していく見込みだ。ただ、その間のハードルは決して低くない。中建審WGのメンバーに、サブコンからは、建専連の岩田会長ただ1人しか参加していない。専門工事業の中でも、民間の改修工事の元請けが多く、業法許可が要らない500万円未満の工事が中心の塗装業界は特殊な業種だろう。どのような施策が担い手確保に役立つのか、業界の事情をアピールしていくことが大切だ。 (合田)